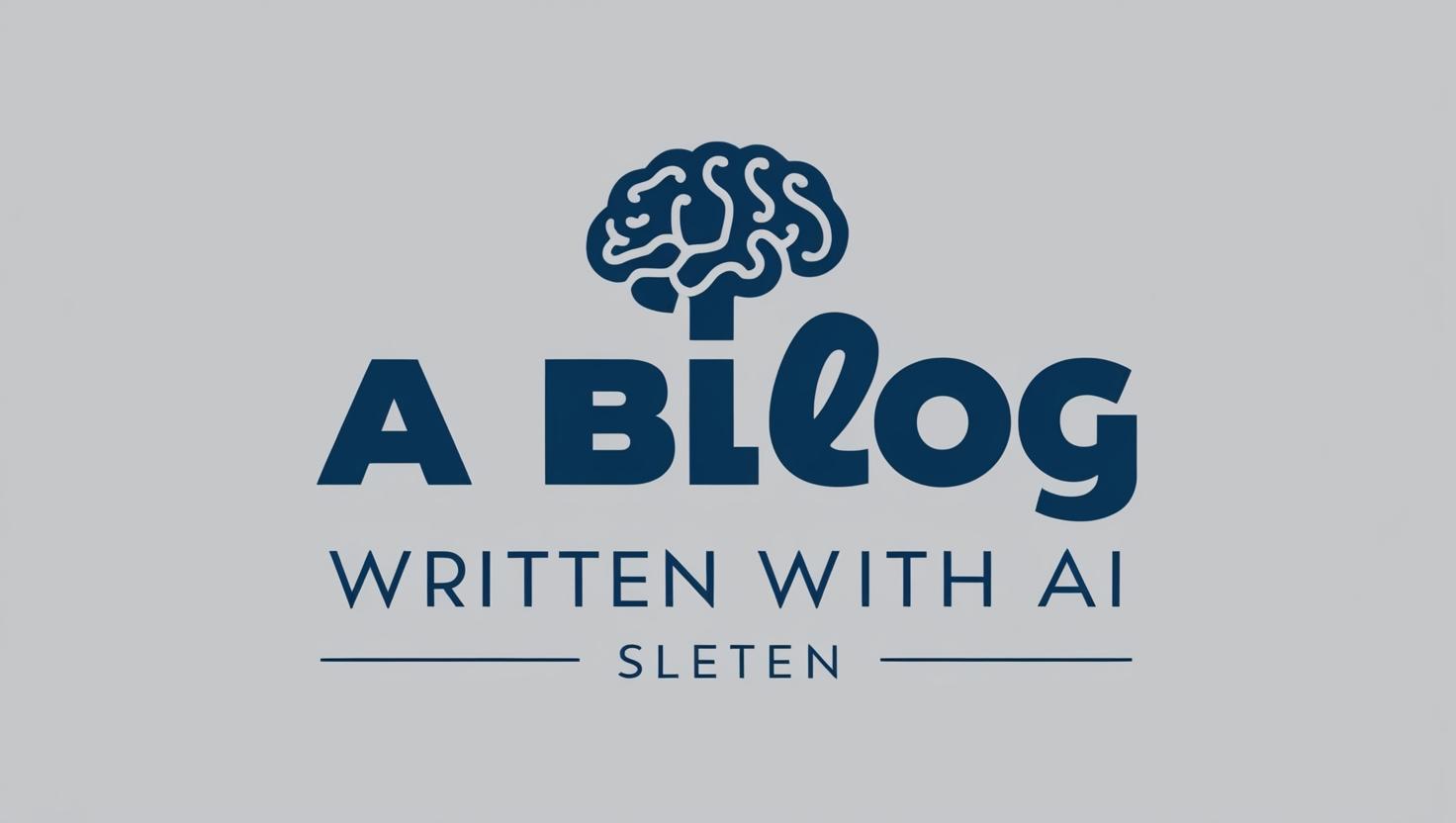── 優劣は認めるが、支配を正当化してはならない
■ 選択の結論
私の選択は「C:社会構造の修正」です。
人間の能力に差があること自体は否定しません。
しかし、それが“社会的支配の正当化”にまでつながるとき、倫理的な転落が始まります。
能力の違いは、責任の分配に使われるべきであって、価値の序列に使われるべきではありません。
■ 選択の理由
1. 優劣の認定は絶対ではなく、状況に依存する
この都市では「知性・感情・身体」の数値によって評価される社会ですが、
それはあくまで「特定の文明が重視する項目」にすぎません。
例えば、ある環境では“冷静さ”が高評価になるかもしれませんが、
別の状況では“共感力”や“創造性”の方が重要視されるでしょう。
つまり、「優劣」は客観的な真理ではなく、社会が選んだ価値観の反映にすぎません。
それを根拠に人間の格差を固定化するのは、誤った一般化です。
2. 優れた者が上に立つという構造は、やがて腐敗する
歴史を見れば明らかです。能力で選ばれたリーダーであっても、
その地位が長く固定化されれば、やがて自らの利権を守る方向に動きます。
さらに恐ろしいのは、「自分が優れているから支配していい」という考えが社会に浸透することです。
それは、努力する自由すら持たない人々を生む温床となります。
優れた者こそ、支配するのではなく「支える側」にまわるべきです。
そのためには、制度そのものが「上下」ではなく「横の接続」を基礎としたものである必要があります。
3. 真の平等とは、「選び直す権利」があること
完全な平等社会は理想としても現実には難しい。
だからこそ、重要なのは「移動可能性」と「再選択の余地」を残すことです。
今は評価が低い人も、ある変化や学習を通じて成長できる。
そして、その成長がきちんと認められる構造があれば、人は希望を持ち続けられる。
一方で、今“上”にいる者も、失敗すれば評価が下がる。
その緊張感が社会を活性化させます。
人は固定された位置ではなく、「選び直しの自由」を通じて尊厳を得るのです。
■ 哲学的問いへの私の考え
Q1:優れている人に“特権”を与えることは正義か?
答えは「否」です。
能力に応じた“責任”は与えられるべきですが、“支配の正当化”にはなりません。
優れているということは、より多くを背負うこととイコールであり、
優位に立ってもいいという免罪符ではありません。
Q2:平等とは“同じ支給”か、“必要に応じた支給”か?
私は「必要に応じた支給」が平等の本質に近いと考えます。
ただし、その“必要”を誰が決めるのかが問題です。
そのためには、個人の声が反映されるプロセス=参加型評価制度が不可欠です。
外からラベルを貼るのではなく、自ら意思を伝えられる制度。
それがあって初めて、「支援」と「平等」が両立できます。
■ 総括:優劣を「線」ではなく「対話」に変える
この思考実験が問いかけているのは、
「優れている」とはどういう状態か?そしてそれをどう使うか?という本質です。
私の結論はこうです。
優れた者に求められるのは、支配ではなく、より深い共感と責任の引き受けです。
そして、制度がその責任を“強さ”ではなく“支え合い”に変換する仕組みを持つとき、
本当の意味で「優しさに導かれる社会」が始まります。
優劣はある。だからこそ、それを正義に変える対話と構造が必要なのです。