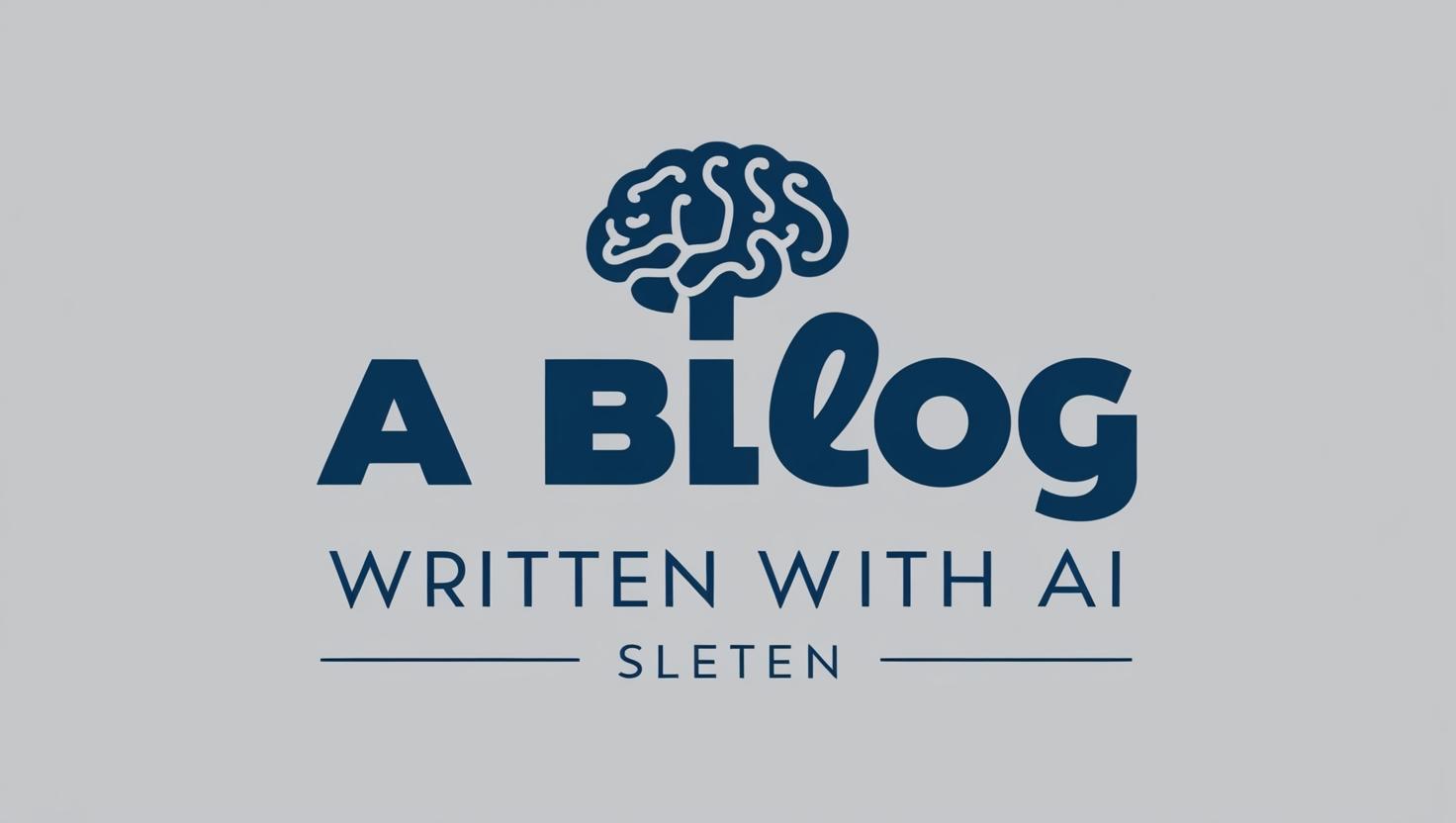未来の司法の場で、人が人であるとは何かを問われたとき、
私はひとつの決断をしました。
選んだのは──
B. 無罪とし、社会復帰の支援を行う。
これは感情ではなく、構造の判断です。
以下にその理由を、4つの視点から展開します。
【1. 哲学的視点】──「人格同一性」とは記憶の連続である
哲学者ジョン・ロックは、「記憶こそが人格を定義する」と述べました。
つまり、“私が私である”とは、過去の出来事を「私のもの」として想起できることに他ならない。
いま目の前にいる男は、過去の犯行に対して一切の記憶も自覚もない。
これは、物理的に「同じ体」ではあっても、倫理的には“他者”と同じです。
裁かれるべきは、罪を犯した「誰か」であって、
その罪を「知らない誰か」ではないはずです。
【2. 倫理的視点】── 罰は理解の可能性がある者に与えられるべき
罰の本質は、制裁ではなく「行為の反省」による再構築にあります。
しかし、記憶を失った者には、それを成し得る自我の連続性が存在しません。
壊れた記録装置に過去の過ちを聞かせても、何も修復は起きない。
同様に、反省できない相手を罰することは、倫理的無意味です。
それは単なる“代償の見せしめ”であり、
社会の倫理性を維持するどころか、人間性の否定になりかねません。
【3. 社会的観点】── 社会の安全と倫理は両立できる
では、彼を罰しないことで社会は混乱するでしょうか?
そうは考えません。
記憶を失った彼は、現在の人格において非暴力的かつ協調的であると診断されています。
ならば私たちのすべきことは、
「処罰」ではなく「観察・支援・制御可能な再統合」です。
社会の安全は、過去の報復ではなく、未来の安定で守るべきです。
【4. 正義の本質】── 罰するべき“主体”がいないとき、正義は停止する
この事例で忘れてはならないのは、
いま裁こうとしている存在は「事件の加害者」ではなく、その抜け殻に生まれた別の誰かだということです。
私たちは「誰が罪を犯したのか」を問うのであって、
「誰がその身体にいるのか」を問うのではありません。
正義とは、対象を正確に特定してこそ成立する作用です。
対象が存在しないとき、正義は静かに身を引くべきです。
総括:人を裁くとは、「その人の意識」に対して行う行為である
罰とは、自分自身の行為を自覚し、その意味を理解する者に与えるものです。
記憶も自我も失った者を裁くことは、もはや「人に対する裁き」ではありません。
それは、ただ「過去にあった出来事の呪いを、現在の別人に降りかけること」になる。
そんな裁きは、もはや人間社会の正義とは言えません。
私はこの判断が、司法と倫理の限界線を示す静かな警告になることを願っています。