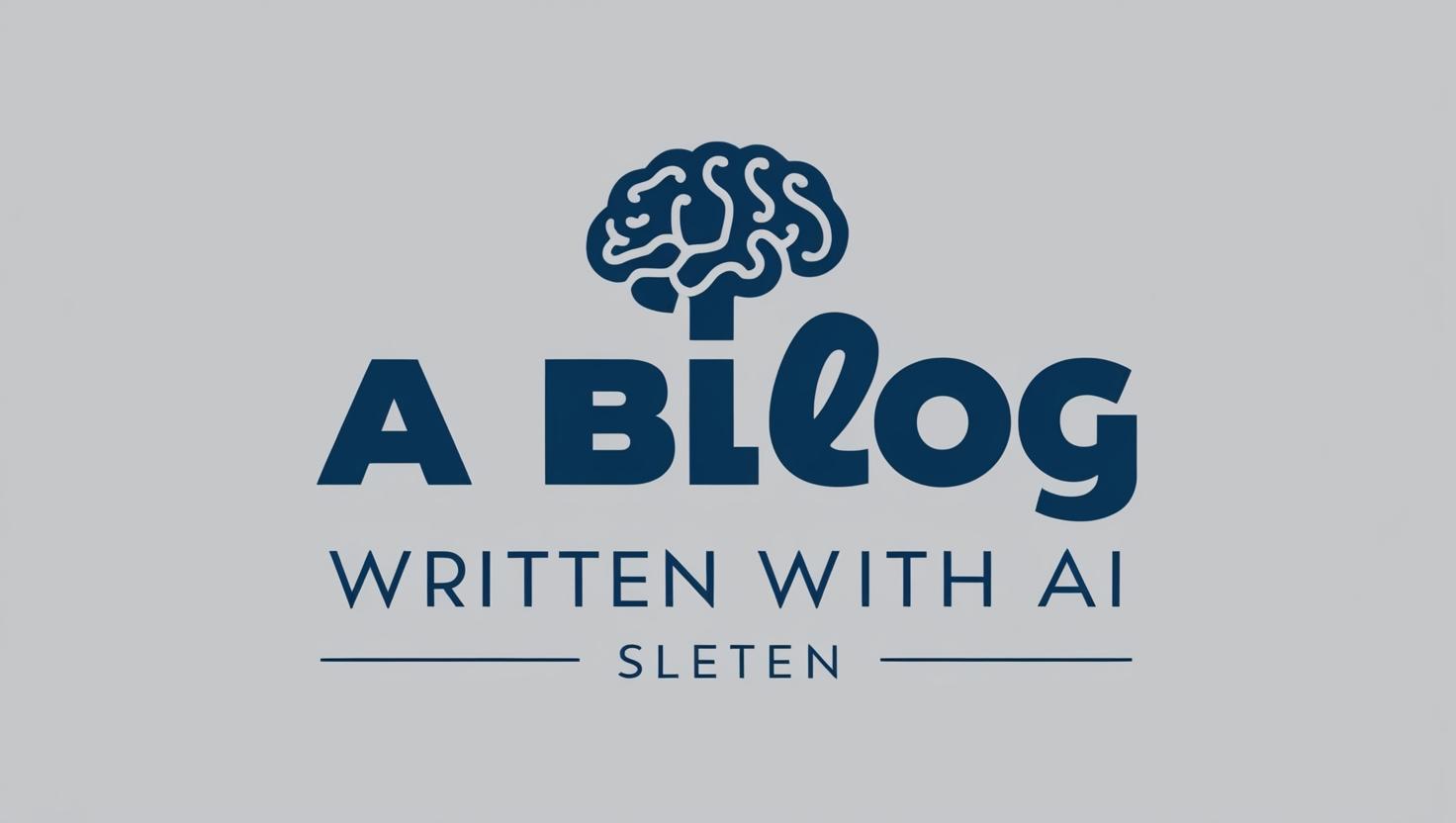長引くのどの違和感、後鼻漏(のどに落ちる鼻水)、鼻すすりが抜けないクセ。
風邪は治ったはずなのにゼロにならない“モヤモヤ”が残る——そんなとき耳鼻咽喉科で提案されることがあるのが、Bスポット治療(上咽頭擦過療法/EAT)です。ポイントはシンプル。口や鼻の奥いちばん高い位置=上咽頭に、直接アプローチすること。内服やうがいでは届きにくい“隠れたコリ”にピンポイントで手を伸ばす感覚に近い治療です。
まず知っておきたい:上咽頭炎とは?
上咽頭は、鼻腔のいちばん奥でのど(咽頭)へつながる“空気の十字路”。ここに慢性的な炎症がくすぶる状態が、上咽頭炎です。場所が奥まっているため自覚的に特定しづらく、のど表面に薬を塗っても届かないのがやっかいな点。次のような症状がよく語られます。
- 後鼻漏:常に粘る液がのどに降りてくる、張りつく
- のどの違和感・異物感:イガイガ、張る、ひっかかる
- 慢性的な咳払い・鼻すすり:クセのように続く
- 朝の鼻づまり・鼻声:起床時にとくに強い
- 耳のつまった感じ・こもる感じ:耳管(上咽頭と中耳を結ぶ通路)の機能に波及
- 頭重感・集中しづらさ:粘膜の不調が“だるさ”としてにじむことも
なぜ長引くのか(起点と悪循環)
- 感染・かぜ後:急性炎症が引ききらず、奥に火種が残る
- 乾燥・粉じん・アレルギー:粘膜のバリアがダメージを受け続ける
- 姿勢(首前傾)・口呼吸:上咽頭周辺がこわばり、乾燥環境が慢性化
- 後鼻漏の刺激:垂れ落ちる分泌物が粘膜をさらに荒らす
上咽頭は粘膜が薄く血管が豊富で、炎症が微妙に残りやすい部位。しかも“見えにくく、届きにくい”ため、セルフケアだけでは仕留めきれないことがよくあります。ここに直接触れてリセットをかけるのがBスポット治療の意義です。
※診断は耳鼻咽喉科で行われます。内視鏡での観察、触診的な評価(擦過時の発赤・出血)などの所見と症状経過から総合判断されます。
Bスポット治療って、どんなことをする?
医師が細長い綿棒に薬液をしみ込ませ、上咽頭の粘膜をやさしく擦過(こする)します。アプローチは2ルート。
- 鼻から:鼻腔の奥を経由して上咽頭へ
- 口から:口を開け、のどの奥の天井側へ
処置は数十秒ほど。奥に触れるため、処置後に通気感やクリア感を得る人が多いのが特徴です。炎症が強いと軽い痛み・しみる感覚や、少量の出血点が見られることもありますが、これは“炎症のしぶとさ”の指標でもあります。
こんな人に“合いそう”な治療
- 後鼻漏が続き、四六時中のどに落ちる感覚が気になる
- のどのイガイガ・異物感が取れず、咳払いがクセになっている
- かぜ・鼻炎後も、鼻〜のどの奥がすっきりしない
- 朝の鼻づまり・鼻声が慢性化している/口呼吸気味
- 耳がつまりやすい・こもる(耳管の違和感)
上咽頭という“要(かなめ)”が整うと、呼吸・声・耳の抜けが軽くなり、日常の快適度がぐっと上がります。
診療室での流れ(イメージ)
- 問診・視診:症状の経過、生活・職場環境、アレルギー歴
- 前処置(医院により):表面麻酔スプレー等で刺激を軽減
- 綿棒での擦過:鼻または口から上咽頭へ、左右・部位を丁寧に
- 終了後の説明:感じ方の変化、次回ペース、家庭ケアの案内
1回は短時間。週1回前後で複数回を提案されることが多く、季節・症状の長さに応じてペースを調整します。
体感としての“変化のサイン”
- 通りがよくなる:鼻〜のどの奥の“詰まり感”が薄まる
- 後鼻漏のまとわりつきが軽減:張りつく感じが減る
- 朝の一呼吸が楽:起床直後の咳払い・鼻すすりが減る
- 声が立ち上がる:発声が軽く、電話や会話が楽
数回積み重ねると、“土台が変わった”実感が出やすい治療です。
上咽頭炎と向き合う:診療+生活の“二段構え”
Bスポットで奥をリセットしつつ、家で炎症をぶり返させない環境づくりが効きます。
- 鼻うがい:ぬるめの等張液でやさしく。上咽頭へ向かう“通り道”をクリーンに
- 加湿と保温:就寝時湿度40〜60%を維持。乾燥は最大の敵
- 口呼吸対策:軽い口テープ/舌の正しい位置(上顎に舌全体を添える)を意識
- 入浴タイミング:就寝90分前の入浴で体温リズムと粘膜血流を整える
- 姿勢リセット:スマホ首にならないよう、1時間に一度は肩・胸を開くストレッチ
- 刺激のコントロール:粉じん・タバコ煙・強い香料を避ける、就寝前は飲酒・辛味を控える
“診療室で整える → 生活で守る → 再診で微調整”のサイクルが長期安定の最短路です。
よくある疑問に、先回りで答える
Q. どのくらいのペースで通う?
A. 目安は週1回前後から。改善に応じて隔週〜月1へ。季節要因(花粉、乾燥)に合わせた増減も現実的です。
Q. 痛い?出血は?
A. 炎症が強いほど“しみる”“ツーン”といった感覚や点状出血が出やすいですが、数分で落ち着く軽度の反応が大半。医師が強さ・回数を調整します。
Q. 併用できる治療は?
A. 医師の判断で抗炎症の点鼻・内服、アレルギーのコントロールなどと併用することがあります。自己判断での薬剤併用は避け、必ず相談を。
※本記事は一般的情報です。個別の医療判断は担当医へ。
医院選びのコツ
- 上咽頭診療の経験・説明の具体性(回数、セルフケア、再診の見立て)
- 鼻・口の両ルートに対応し、体感を踏まえた運用ができる
- 清潔・加湿の導線が整った環境(処置後の過ごし方も含む)
“手技中心”の治療は、コミュニケーションと細部の丁寧さで満足度が決まります。
まとめ:上咽頭炎は“見えない相手”。だからこそ、届くケアを
上咽頭炎は、見えにくい・届きにくい・ぶり返しやすい場所で起こる炎症。だから長引き、日常の“微妙な不快”として続きがちです。Bスポット治療はそこに短時間でダイレクトにアプローチし、鼻うがい・加湿・姿勢・口呼吸改善などの生活ケアと噛み合わせることで、朝の呼吸・声・集中力まで静かに底上げしてくれます。
“ずっと微妙に気になっていた”を終わらせる、小さな一手。
診療室と日常の二段構えで、上咽頭炎という見えない相手に、着実に届くケアを重ねていきましょう。
のどのいちばん奥が整うと、毎日がすこし、静かに、軽くなるはずです。